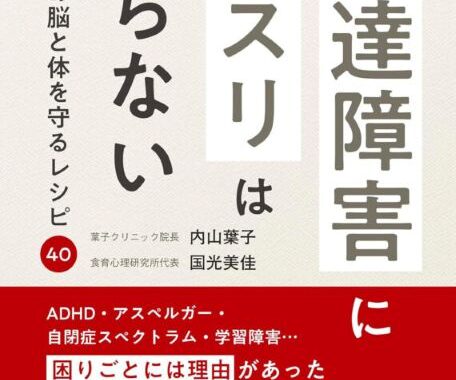有機農業のあるべき姿とは~持続型社会はオーガニックからvol.4
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.13
2024年11月 業務執行理事 南埜 幸信
(4)山室真澄氏の著書「魚はなぜ減った?」より
近海の魚が極端に減ってきている現状の報告を各所からいただくなかで、たいへん興味深い書物に出会った。東京大学の山室真澄教授の「魚はなぜ減った? 見えない真犯人を追う」という著書である。シジミの一大産地、島根県の宍道湖で起きていた変化。その背景にはミツバチ大量死で広く知られるようになったあの農薬が深く関係していたというのだ。
この東京大学の山室真澄教授らの研究成果は、2019年、世界で最も権威のある学術誌のひとつ「Science」に掲載され、大きな話題となった。宍道湖の釣り人が万全と不安を感じながらも、確証を得られずにいた農薬の影響を、山室先生らのチームが、客観的なデータで示したもので、我が国の水辺の将来を考えるうえで、間違いなく重大な意味をもつ研究成果である。
島根県の宍道湖では、1993年からウナギとワカサギの漁獲量が激減していた。この原因が、同時期から水田で使われ始めた「ネオニコチノイド系殺虫剤」が原因ではないかという山室先生の仮設から研究が始まった。このネオニコチノイド系殺虫剤は、皆さんもご存じのように、昆虫には強い毒性を発揮するのが特徴で、現在では広く使用されている農薬である。つまり、かつて使用された生物の生存そのものに影響を与える強い毒性のある農薬とは違い、このネオニコチノイド系殺虫剤が直接ウナギやワカサギなどの魚を殺したのではなく、水中の生態系と食物連鎖の乱れから、結果として魚が激減したのではないかという研究である。
農薬が生物に与える影響を理解するには、「食物連鎖」の知識が欠かせない。そしてこの自然界における食物連鎖は、本来、複雑な構成要素から成り立っているために、因果関係を特定するのは困難を極める。しかし、宍道湖については、特有の自然条件から、食物連鎖の構成要素がシンプルであったことにより、ネオニコチノイド系殺虫剤が生物に与える影響について、効果的な調査ができたのである。
まずは、宍道湖の底生生物の調査から、ヤマトシジミが90年代以降に徐々に減少。エビ類は93年に激減していたという変化が報告されていた。また、漁獲対象種以外の底生動物を調査した結果、オオユスリカ(あかむし)をはじめとする節足動物はすべての種が減少していた。特にオオユスリカは、1992年までは毎年大量発生していたが、1993年以降の調査では突然生息が確認されなくなったというのである。この異変が起きたタイミングは、まさしく水田用ネオニコチノイド系殺虫剤が初めて使用された時期と一致している。さらに容疑者をネオニコチノイド系殺虫剤とする証拠として、ネオニコチノイド系殺虫剤が使用開始された1993年に、ワカサギとウナギは激減したが、シラウオは減少していない。つまりは、ワカサギとウナギの激減の原因が、そのエサとなる生物(動物プランクトン、ユスリカ、底生動物)がネオニコチノイド系殺虫剤によって減少したためである蓋然性が高いのである。さらに、一部の魚類のみの急激な減少は、湖岸改修や農地整備の効果とは考えにくい。また、汽水の宍道湖には、ブラックバス等の魚食性外来魚は定着していない。
また、決定的な証拠として、宍道湖の湖水を調査した結果、ネオニコチノイド系殺虫剤の成分が検出され、その1993年当時の推定濃度は、ワカサギやウナギがエサとしている生物が影響を受ける可能性が高いというのだ。
これらの研究成果から、宍道湖のワカサギとウナギの激減は、そのエサとなる生物の激減が原因であり、それをもたらしたのは、水田におけるネオニコチノイド系殺虫剤である疑いが大きいという結論である。過去の農薬と違い、ネオニコチノイド系殺虫剤が直接魚を死に至らしめたのではないために異常が発覚するのが遅れたのだ。このように、生態系の異変の原因を突き止めるには、化学物質の影響や物質循環的な観点からもデータを出して根拠をしめさなければならないが、それを分析できる生態学者はまだ少ない。魚類の保全は、生態系全体を把握することが必要で、それは研究自体の対象が大きすぎて、しかも生態系は複雑系の生命体のメカニズムであるので、なかなか科学的な研究は難しい。むしろ、釣り人が日々行っている情報収集や釣り場の記録が、将来水辺に迫る異変に気付くきっかけになるかもしれない。
房総半島周辺の近海で起こっている釣り人たちの話。「魚がめっきり捕れなくなった」は、陸で農業を続ける私たちにとって、重大な課題と受け止めるべきなのである。
次号に続く