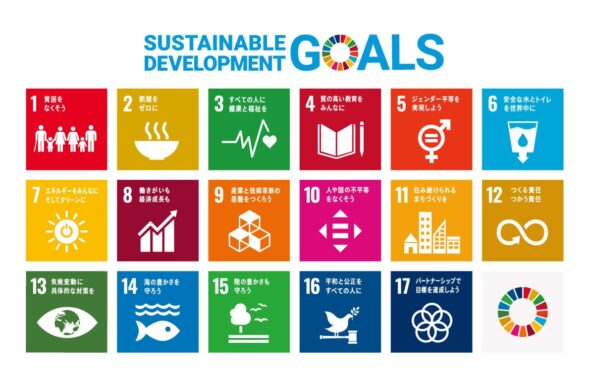みどりの食料システム戦略誕生の背景 Farm to Fork vol.2
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.16
2024年12月 業務執行理事 南埜 幸信
持続可能な⾷品加⼯・卸売り・⼩売り・ホスピタリティー・フードサービスの促進
⾷品加⼯・卸・⼩売り・フードサービスといった部⾨については、以下の内容を提起している。まず、⾷品事業者・業界に対して、環境フットプリントを削減するための道筋を示す対応を求めている。例えば、健康的で持続可能な⾷品の選択肢や、安価で⼊⼿しやすいものを増やすことだ。
また、エネルギー効率の強化、社会的弱者や健康⾯で不安を抱える⼈のニーズをくみ取ったマーケティング戦略に改めること、⾷品の値引き販売によって⼈々の⾷品に対する価値感を過少にさせないこと、梱包(こんぽう)を減らすこと、といった対応を求めている。
特に梱包の削減は、新しい循環経済⾏動プラン(2020年6⽉4⽇付地域・分析レポート参照)に即したものにする必要がある。とりわけ⾁類に関して、「⾮常に低い価格で宣伝するキャンペーンは避けなければならない」とし、消費抑制の⽅向性を明確にしている。
欧州委はまた、上記に関する⾷品事業者の取り組みをモニタリングする。不⼗分な場合は法制上の措置を検討する。例えば、⾷品事業者の企業戦略の中に持続可能性を含めることを求めること、脂肪や糖、塩分の多い⾷品の販売促進を制限 するために「栄養プロファイル制度」の導⼊を検討することなどに取り組むとした。
栄養プロファイルとは、栄養構成に応じて各⾷品をスコア化し、⼀⽬でその⾷品の健康レベルや栄養レベルが分かるようにするものだ(下図参照)。EUでは、2006年に⾷品の栄養や健康に関する強調表⽰に関する「欧州議会・理事会規則(EC)No1924/2006」が成⽴した際、2009年1⽉までに栄養プロファイル制度を導⼊することとされた。しかし、 全ての⾷品を統⼀的にスコア化する基準作成の難しさから、いまだ実現に⾄っていない。他⽅、フランスやベルギーなど⼀部の加盟国では、EUの統⼀基準を待たずに独⾃の栄養プロファイル制度を既に導⼊済みだ。
このため、EUとしては、栄養プロファイルの域内共通ルールを早急に作成する必要がある。そこで、今回のFTF戦略に よってあらためて道筋を⽰されることになった。FTF戦略では、2022年第4四半期(10〜12⽉)までに域内共通の栄養プロファイル制度を法制化するとした。EU全域で同制度が義務化されれば、EU域外からの輸⼊⾷品にも同様のスコアを付すことが求められ、EU向けに⾷品を輸出する事業者にも対応が求められるであろう。
図:栄養プロファイルの例
栄養⾯で最も優れた⾷品にAが付され、最も劣る⾷品にEが付される。

出典: Santé publique France Nutri-Score, c’est quoi ?
そのほか、特に⾷品包装に関して、関連規制の改正による⾷品の安全性と公衆衛⽣の向上や、再利⽤・リサイクル可能 な素材を使った⾷品包装の使⽤の⽀援、フードサービスでの再利⽤可能な包装・⾷器の使⽤に関する法整備などの取り 組みを掲げている。加えて、持続可能性や⾷品ロス削減の観点からの農⽔産物の販売基準⾒直しや、地理的表⽰(GI)制度への持続可能性 に関する基準導⼊の検討、⾷品の1次⽣産から販売に⾄るまでの⾷品供給⾏程の短縮への⽀援なども掲げた。
次号に続く