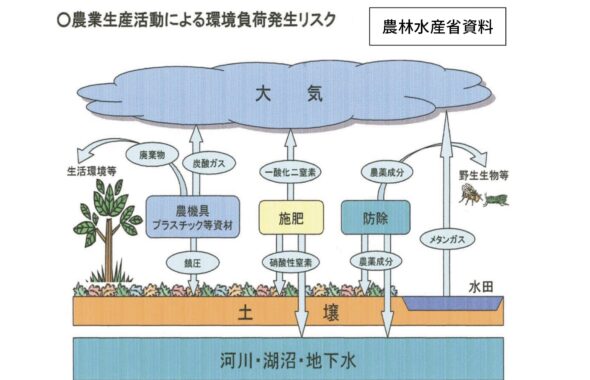みかんの不作に思うこと
みどりの食料システム戦略の実践レポート vol.22
2025年1月 業務執行理事 南埜 幸信
つい3週間ほど前の昨年の年末。日本一と言われる東京の大田市場を見て回って驚いたこと。これほど市場の現場にみかんの無い年末が今まであっただろうか?日本人の年末からお正月の風物詩としてコタツにみかん。テレビの特番をみながら、暖房の部屋では喉が渇くのでコタツでみかんを食べながらという楽しみ。
みかんはある意味正月商材で、金時人参やヤツガシラ等のように、年末のみかんの欠品などかつては取引先からは許されなかったほどである。それほどの商品なので、当然年末の大田市場にはみかんがあふれているそんな光景が当たり前だったので、今年の異様さは一層記憶に残ってしまった。
当然価格も暴騰している。しかも、この価格高騰は、何も農家の収入アップにはなっていない。それは、そもそも価格が高くても、出荷できるものが無いからだ。しかも不足しているキャベツや玉ねぎは中国などからどんどん輸入されているが、温州ミカンは日本のオリジナルな果実。外国からの輸入の道はほぼ無い。
昨年のみかんの記録的大不作。その原因は大きく二つといわれている。一つはカメムシの大発生にある。このカメムシ大量発生の直接的な原因としては、一昨年から昨年にかけての高温傾向だ。昆虫は変温動物なので、気温が高いことで生育のサイクルが早くなり、そのぶんカメムシの世代数と年間の発生数も増える。更に以前の年からの影響もあった。一昨年の夏は過去最高の暑さ、また‘23年12月〜’24年3月は過去2番目の暖冬であった。夏に増えたのに加え、暖かい冬のおかげで越冬できる数が増え、それが大量発生につながったと考えられる。
また、『果樹カメムシ類』については一昨年の夏に、カメムシ幼虫の餌となるスギやヒノキなど針葉樹の球果が豊作だったことも要因と考えられている。このカメムシの大量発生により、果樹園での被害や収穫量への影響が出てしまったのだ。カメムシ大量発生注意報の出ている『果樹カメムシ類』とは、チャバネアオカメムシやツヤアオカメムシ、クサギカメムシなどで、モモやナシ、リンゴ、カンキツなどの果実にストロー状の口を刺して吸汁し、それが果実の傷やへこみ、落果などの原因となる。つまりは、カメムシの大量発生により、果実の着果数が激減し、また、出荷できない品質のものが多く出てしまったということである。実は杉やヒノキは花粉症だけではなく、カメムシの幼虫の餌となっていることに改めて問題の深刻さと、ここまでくるとこれは人災ではないかとも思えてくる。特に杉は植林により人為的に急増したものだからだ。
次の原因としては、まさしく異常高温による果実の『ヤケ』である。みかんの表皮が直射日光と高温により、いわゆる火傷現象を産み、果実の正常な成長と成熟を阻害し、結果としてこれも、出荷できない果実を多く出してしまったのである。私も実は、昨年の9月に、熊本県の日本最大の有機みかんの生産者の圃場にお伺いして、その異様な光景に、おもわず言葉を失ってしまった。9月なのに、まだ暑いのに、みかんの果実が黄色くなっていたのだ。通常は、もともとみかんの果実は緑色をしていて、それが生育とともに、低温の影響を受け、ちょうど秋に葉が紅葉するように、果実の表皮も黄色くなってきて、さらに朝晩の寒さが強くなってきて全体が黄色くなるというのが正常な登熟。これが、まだ残暑の残る9月に、果実の1/3程度が既に黄色くなっていた。明らかに異常事態だ。果実の表皮がヤケてしまったのだ。さらに表面だけではない。果肉まで高温による生理障害を起こしていた。
過去の人類の農業の営みの中で、これほどの短期間で、これほどの温度上昇はたぶん経験したことがないであろう。30年~50年程度かけたゆっくりとした気温の上昇は、過去は高温耐性の品種改良や栽培技術の工夫によって人類は対応してこられたと思う。しかし、現代は過去に経験したことのないスピードで、気温の上昇と環境の変化の中に、農業だけではなく、あらゆる生命の存在が揺らぎ始めている。楽観論者の言説に惑わされることなく、過去の想定されたスピードでは対応しきれないという事実に、そろそろ正面から向き合うことが自然界から要求されているのだ。過去の延長に未来が来るのではなく、この変化のスピードに対応できないと、未来は無いということだ。
過去の日本の農業技術は、寒い冬をどのように超えるか、つまり、ハウスやトンネル栽培や暖房設備など、温める技術の開発や設備の普及が主流の技術開発であった。しかし、これから求められるのは、光合成の活動を妨げないように一定の日照は確保しながらも、いかに温度を下げられるかという農業技術である。この課題への知見は残念ながらほとんど積みあがっていない。この現実を社会が認め、いかに気候の変化に追いついていけるスピードで技術革新を達成できるか。農業の未来はここにかかっているのである。
次号に続く